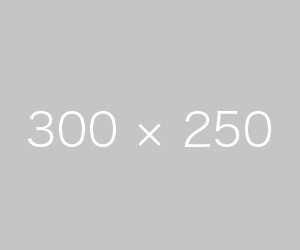立屋学校(立屋分教場):沿革
| 1800年代 | 寺子屋の歴史に立屋の寺子屋があり、 師匠、鈴木八右衛門、村越九郎右衛門の名前が出てくる。 主に読み、書き、文章を教えていたようです。 |
| 明治15年11月(1882年) | 立屋学校始まる。 小川学校 立屋支校となり民家仮用で始まる。 (場所は古老の話によると小立屋の上部、村道S字周辺とのこと) |

立屋学校跡地

移築分教場
| 明治 | 19年4月 | 高府、小根山連合村 (上水内郡大16番学区) 高府尋常小学校、高府本校、小根山支校、立屋派出所となる。 |
| 20年12月 | 派出所改め、簡易小学校となり、高府尋常小学校、立屋簡易小学校となる。 | |
| 25年 4月 | 南小川尋常小学校、立屋分教場となる。 | |
| 29年 | 南小川2校制となり、高府尋常小学校、小根山尋常小学校、小根山の立屋分教場となる。 | |
| 35年 6月 | 南小川2校が尋常高等小学校を開設する。 | |
| 41年 3月 | 義務教育年限6年となり、尋常科6年とし、高等科2年を併設 | |
| 43年 6月 | 南小川尋常高等小学校1校制となる。 本校ー釜房 小根山分教場(4年) 立屋分教場(3年) 他に、花尾、久木分教場 各3年までとなる。 |
|
| 大正 | 2年 3月 | 南小川本校校舎完成、新校舎で授業始まる。 |
| 児童数 尋常小学校 男 221人 女 168人 計 390人 高等小学校 男 46人 女 4人 計 50人 |
||
| 立屋分教場廃止 最後の生徒は小林徳義、村越甲子とのこと。 立屋廃校後、表立屋は小根山分校、裏立屋は本校へ通うようになった。 原因や時期は不明 |
||
| 昭和 | 16年 | 国民学校令により、尋常高等小学校が国民学校と改称 |
| 22年 | 教育基本法 公布 小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年となる。 国民学校改め、南小川小学校、南小川中学校となる。 |
|
| 30年 | 南北小川村が合併して、小川村となる。 | |
| 31年 | 南北中学校が統合して小川中学校となる。 | |
| 48年 | 南北小学校が統合して小川小学校となる。 |
明治14年12月に長野県は上水内郡内の小学区を84に区画し、各区に本校を一校設置し、土地の状況によって支校を併置させるよう布達した。
小川学校は、上水内郡第66番学区とされている。この関係で明治15年11月には支校を立屋に置き立屋支校と称した。
校舎は民家を使用し、先生は一人だけ、初等科の生徒が通った。
明治18年、長野県は連合戸長役場制を布き、町村連合を進め、高府村と小根山村を一連合村と指定した。
これにともない、上水内郡の場合は従来の84の学区を24の小学区にし、明治19年4月より実施した。
この結果、高府村・小根山村連合村の小学校は高府村に設け、上水内郡第18番学区高府学校と称し、小根山村の学校は小根山支校となり、立屋には立屋派出所を置いた。
明治21年6月4日の学校日誌では「簡易立屋学校授業生欠員に付、本校より授業生小川藤太を派教授せしむ」とある。立屋では授業生一人で教えていたのであろう。
明治28年には小根山分教場分離に関する動きはあわただしくなる。
明治28年3月30日には、村会の全会一致があったから急いで許可してほしいと、郡役所に申請した。
このころには郡役所の方でも認める方針になってきたようで、もっとくわしく説明しろとか、財政基盤はだいじょうぶか、などの問合わせをいくつかしている。
明治29年1月には分離独立がほぼ決定となり、 そのための体裁をととのえる書類がいくつか取りかわされた。
それらによれば、小根山は258戸、 1,501人で、学令児童226名(高府は493名)であった。
これに対し生徒の数は本校140人、立屋18人の計158人(高府は309人)となっている。この数字だけから見ると生徒は学令の62,3%である。
こうして明治29年4月6日小根山尋常小学校が開校した。
県知事に届け出た書類によれば、尋常科四ヶ年で生徒は男61人、女56人、ほかに立屋分教場は20人で計137人。
教育費として571円51銭が計上され、うち給料が三八七円である。
生徒の授業料は一ヶ月一学年三銭、二学年六銭、三学年一〇銭、四学年一五銭であった。
教科は修身・読書・作文・習字・算術・体操で、四年女子にはこの年から裁縫が加わっている。
(「小根山分校開校百周年記念誌もりきっ子」より)